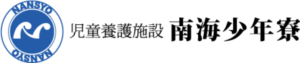令和5年度 南海少年寮 事業計画
Ⅰ.令和5年度基本方針
この数年新型コロナウイルス感染症の影響が多々あったが、この間事業計画が十分に進んでおらず様々な課題が現れてきた。
そこで例年に準じた形ではなく、また、優先すべきことをより絞って取り組むこととする。ただし、継続して取り組むべき事項は進めていかなければならない。
第一に、今年度は入所児童に対する支援体制の再構築を最重要事項とする。年間計画を基にこの1年間で新たな支援体制を構築し、今の時代に求められる「子どもたちが安心できる新たな生活文化」の形成に取り組んでいく。
継続して取り組む事業としては、南海少年寮社会的養育推進計画であるが、地域への小規模化において定員が6名から4名になることなど制度も変化してきており、当初計画からの見直しも必要となる。
新型コロナウイルス感染症に関しては5月から5類に移行される見込みだが、集団生活においてどのように対応していくか情報収集をおこない、精査して対応を考えていかなければならない。
Ⅱ.重点事項、具体的取り組み
① 入所児童に対する支援体制の再構築
※新たな入所児童に対する支援体制の再構築を年間計画に基づいて実行する。
※理念の見直しを進め、職員が同じ方向に力を合わせ、求められる職員像や入所児童への姿勢を明確にしていく。
※児童の声を聞く工夫や機会を増やし、反映できる体制を整える。その上において、グループ活動での児童との話し合いを大切にしていく。
※独自に作成したアセスメントシートの見直しや作成をおこない、それを活用したケース会等をおこないやすい体制を構築する。
※基本的処遇のマニュアルを作成し、各職員が共通理解のもと身につけることが出来るよう努める。
※各委員会の活性化、外部研修の施設内へのフィードバックの方法をあらためて検討し実行に移す。
② 社会的養育推進計画の推進
※南海少年寮社会的養育推進計画に関して、特に小規模化において制度も変化していることもあり、必要な部分の見直しを検討する。
※小規模化検討チームを中心に、調査(情報収集や見学、小舎制養育研究会の活用)、検討等を進めていく。
③ 地域との連携と貢献
※地域の児童や保護者等と共に例年実施してきた南少夏まつりは、昨年度、東町の児童・保護者に絞って実施する予定であったが、実施寸前に新型コロナウイルス感染症の患者数が過去最高になり施設内だけで実施した。今年度は、状況を見ながらではあるが東町の児童・保護者と共に実施したい。
PTA、青少協、三里みらい会議等への協力などは、引き続きおこない地域との関係を大事にしていく。
※防災行事等の実施と共に備蓄品を充実させていき、地域との連携や体制つくりなどの取り組みを検討していく。
※社会福祉法人として地域における公益的な取り組みを実施するにあたり、高知市社会福祉法人連絡協議会の会員として災害対策連携部会に所属し、その活動に取り組んでいく。
Ⅲ.主な事業
① 年間を通しての事業
(1)子育て短期支援事業 (各市町共に委託契約継続予定)
平成7年度より高知市と委託契約済み
平成8年度より土佐市と委託契約済み
平成9年度より南国市と委託契約済み
平成12年度よりいの町と委託契約済み
平成29年度より佐川町と委託契約済み
平成30年度より田野町と委託契約済み
(2)防火訓練(毎月)
年1回防災訓練かそれに代わる防災行事をおこなう。
年1回は風水害に対する訓練をおこなう。
年1回は防犯に関する訓練をおこなう。